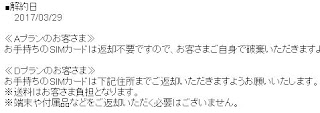2/25発売のWiko Mobile Tommyを使いはじめて6日目になります。手帳ケースに入れてデータ通信のメインとして使っています。このTommyは前評判で「安っぽくない」というところを買って導入したところもありますが、いままで使っていた中国メーカーのものはセキュリティー面での不安が常にあったので、先進国フランスの文化背景をも考え合わせてWiko Mobileの端末に乗り換えました。「個人情報」とかの考えは某国は、まずないですよね。
さて、Amazon販売のWiko Mobile Tommyのブリーンとフレッシュレッドが早くも値下がり、筆者がNTTコムストア goo Simsellerで購入した額とほぼ同じになっています。
goo Simseller(NTTレゾナント)運営サイトのNTTコムストア



 Yahoo!ショッピング内NTTコムストア by goo Simseller>5インチエントリーモデル SIMフリースマホWiko Tommy+選べるOCNモバイルONEセット 【送料無料】
Yahoo!ショッピング内NTTコムストア by goo Simseller>5インチエントリーモデル SIMフリースマホWiko Tommy+選べるOCNモバイルONEセット 【送料無料】


OCNモバイルONEに新規で加入する場合には、メリットがありますが、そうではない場合、任意とはいえOCNモバイルONEに加入しないといけないのかもしれないと思ってしまうユーザーとっては選択肢から外れることになります。筆者も去年、ここのセット販売で格安スマホを購入して加入はしないつもりでしたが、以前利用していたときとの比較がしてみようと、数ヶ月のつもりで加入しましたが、以前よりもデータ通信速度はあがっているようで快適なので、そのままデータ通信のメインで使っています。
さて、Tommyについてですが、価格帯から背面カバーがプラスチック製であったりとコストカットの影響はありますが、前評判通り安っぽくはないです。動作そのものは安定していると言えます。センサーにジャイロスコープも搭載しているので、ポケモンGOのARでプレイできますし、GPS起動にももたつきがないなど、しっかり最適化されているのではないかと思える出来になっています。ゲームなど以外での基本動作は、一通り問題ない感じです。ホームボタンのダブルタップでスリープし、スマートジェスチャーで復帰することができるので、そこら辺も万全のようです。
SoCのSnapdragon 210の1.3GHz(クアッドコア)版に不安を持つユーザーも少なからずいると思いますが、筆者も目をつぶるつもりでいたものの、実機の操作感は、ひとつ上位のSnapdragon 410の1.2GHz(クアッドコア)よりも、やや良い感じです。OSやアプリの起動では、若干時間がかかる気がしますが、起動してしまえば割とキビキビとした動きでストレスを感じないです。
筆者は、Tommyのトゥルーブラックを使っていますが、この背面カバーの表面にはシボが入っていて、皮状の仕上げで、シックな感じになっています。しかし、仕上がりは良いですが、デザインとしては、特に尖がったところもないですし、やはり無難な感じといったところでしょうか。筆者は、手帳型ケースに入れて使っていますので、いまのところ外観にはそんなにシビアにはなっていません。
さて、通信面では筆者は、IIJmioタイプA(au 回線)SMS付データ通信SIMで、Tommyを運用しています。つまり、この端末はマルチキャリア対応のものです。確認はしていませんが、au VoLTEに対応しているらしいということです。また、ドコモの3GFOMAプラスエリア(Band6)には対応していないのため、山間部などBand6でカバーしているところでは、つながらないと思います。例えば、人気のある登山コースの山頂ですとか、山間部にある美術館や学校などの施設をBand6でカバーしていますので、そういうところでは通話やネットができないと思います。
6日間使った印象では、筆者が日ごろ使っているアプリでは、動作も軽く問題ないレベルにある性能だと言えます。ゲームでは、GPS機能をチェックもかねてポケットGOをプレイしていますが、初期画面のマップの読み込みにもたつくぐらいで、モンスターボールを投げるARモード画面ではもたつくこともなく普通にプレイできますね。しかし、ゲームで3D性能が求められると、SoCのSnapdragon 210では、ひとつ上のSnapdaragon410でさえ、そんなに3D性能が良いわけではないので、動作クロックが1.3GHzとはいえ期待できるところではないと思います。実際に試してみていくしかないところではありますね。いまのことろ動作面で気になるようなところは、スマートジェスチャーでの復帰に手間取ることぐらいでしょうか。
価格とマルチキャリア対応ということから、iPhoneなどの予備機として、またはSNSやブラウジングなどのデータ通信用端末として十分な品質を持っているものだと思います。いままで使っていた某国製メーカーのスマホは、アプリもよく落ちるし、先にもあげたようにセキュリティー面での不安がありますので、管理も数多くなって難しくなってきたことからデータを移し終えたら処分する方向で動いています。